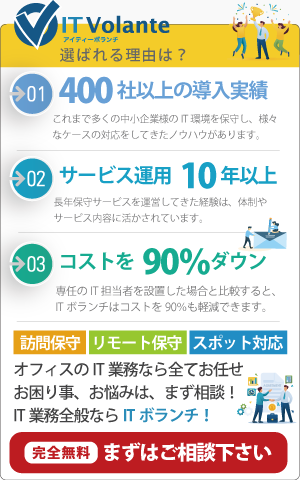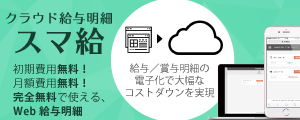2020年に始まり2023年に一旦は収束した新型コロナウィルスの猛威は世界の生活環境に大きな変化をもたらしました。中小企業においてはコロナ禍がもたらした最も大きな変化はテレワークの導入だと言えるのではないでしょうか。
コロナ禍以前は遅々として導入が進まなかった中小企業のテレワーク導入ですが、非常事態宣言の発令などにより、テレワークの導入を検討せざるを得なくなったことにより導入が一気に加速しました。
しかし予期しなかった急速なテレワークの導入は弊害も多く見つかっており、下記のような課題が浮き彫りとなりました。
- 就業規則の整備が追いつかない
- 社内ネットワーク環境がテレワーク前提で構築していない
- ノートPCの手配が半導体不足により停滞してしまっている
- ストレージを社内に設置しておりファイル共有に負荷がかかっている
特にテレワーク導入により多くの社員が自宅から社内のファイルサーバやNASに接続する事態になり、ネットワーク環境やストレージ環境などの負荷やセキュリティの課題が多発し、対策を必要とする状態になりました。
しかし、そもそもファイル共有環境としてファイルサーバとNASの違いを明確に説明できる方は多くはないのではないでしょうか。双方のメリット・デメリットを含め、正しく理解することはITコストの最適化を図れるだけでなく、貴社事業の業務効率化にもつながる可能性があります。
今回はあなたが最適なファイル共有環境を用意できるよう、ファイルサーバとNASの違いについて詳しく解説していきます。
□■□■IT業務のお悩みやお困りごと、コスト削減をお考えなら、解決手段をご紹介します!まずはITボランチへご相談(無料)ください。無料でのご相談はこちらから□■□■
Contents
ファイルサーバーとは?NASとは?
ファイルサーバーとNASは全く違うIT機器という認識を持っている人も少なくないのではないでしょうか。実は半分正解で半分間違っています。まずはファイルサーバとNASの概要を解説していきます。
ファイルサーバーとは
ファイルサーバーとは「ネットワーク間でファイル共有機能を有している仕組み全般」を表します。インターネットに接続していることが多いので「ファイルサーバー=インターネットに接続しているもの」と認識している方もいらっしゃるかもしれませんが、社内といったローカル環境限定でも複数デバイスでファイル共有ができるシステムがオンプレミスで構築されていればそれもファイルサーバーといえます。
ファイルサーバーとしたグループに含まれるものは、ITの急速な進化に伴い多様化しています。
- 自社でサーバーを購入して専用のファイルソフトをインストールして作ったもの
- サーバーをレンタルして専用のファイルソフトをインストールしたもの
- 契約するだけですぐ使えるクラウドストレージ(オンラインストレージ)
といったシステムはすべてファイルサーバーに該当します。
NASとは
NASとは正式名は「Network Attached Storage」といい、「ネットワークに接続して使う、ファイルの保存・管理に特化したストレージ」といった特徴を持つ機器を指します。NASを説明するときに「ネットワークに接続して使うHDD」と説明している記事がありますが、厳密にはSSDタイプも販売されているので、記憶媒体の種類は関係ありません。
NASは法人用だけでなく、家庭用としても販売されており家電量販店で入手可能です。大容量のデータ保存ができるように大型になっているモデルも多く、利用するにはある程度のスペースを社内で確保しておく必要があるでしょう。
NAS機能のないストレージだと1台に有線接続してファイルを操作するタイプが多いですが、NASの場合は無線接続で多数の人間が使うことを想定しているのでケーブルレスに使えます。Wi-Fi環境があればすぐにセッティングして外部からもアクセスできるようになるので手軽です。
注意が必要なのは、サポートしているOSを確認するようにしましょう。WindowsのPCはサポートしているがMacのPCはサポートしていないというケースもあります。
ファイルサーバーやNASが企業で重要な理由とは

中小企業などでファイルサーバーやNASの活用が求められているのは、
- デジタル化の加速によりファイル共有が当たり前になりつつある
- 電子帳簿保存法など法律への対応することで必要性が増している
- 様々な書類の電子化によりバックアップを取る必要性が出てきた
といった背景があります。
テレワークを実現するためのIT環境を整備するため、会社で取り扱うデータのデジタル化が急務になり、ファイル共有を必要とする企業は増えています。
また、増加しているサイバー攻撃を防ぐためにも、安全な環境でファイルを保管するという観点でセキュリティ対策にも関心をもち、もただNASやファイルサーバーを導入すればいいという流れではなくなっています。
無料で構築できる構成も認知されており、ファイル共有(データ共有)においてファイルサーバー・NASを使っていない企業はほとんど無いと言えます。
また電子帳簿保存法の改正により、各種書類をデジタルで保管しやすい環境となってきており、これまでの紙媒体での書類からデジタル化したデータとして管理する企業が急増し、デジタルデータの保管先としてファイルサーバー・NASのニーズが高まっているのも要因の1つです。
これらの背景からファイルサーバーを活用することはもはや必須となっており、部署問わず大半の従業員や役員は利用しています。それらの利用するユーザー管理の機能やユーザがどこまでアクセス可能なのか、ユーザーの権限を管理できるような仕組みも急速に進化しており、セキュアな環境のニーズは拡大しています。
さらに企業の機密情報を含めデジタル化が進んでいるため、障害などの発生によりデータ消失してしまうケースも想定し、それぞれのPC・スマートフォン以外にもバックアップ先が必要になってきているのも原因として挙げられるでしょう。
ファイルサーバーとNASの違いとは?

ファイルサーバーとNASの違いは、まず何を指すかで分類可能です。
そもそもファイルサーバーはファイル共有管理機能を有している仕組みそのものを指しています。つまり
- オンプレミスで自社構築したファイル共有システム
- Googleドライブといったクラウドストレージ(オンラインストレージ)
など、ファイルを共有できるものはすべて対象になります。
対してNASはファイルを共有できるストレージ、つまり機器を表しているのがポイントです。NASをベースにしてファイルを共有できる仕組みを構築したら、それもファイルサーバーに該当します。つまりファイルサーバーは仕組みを指すため定義が広く、NASはファイルサーバーを作るための機器となります。ファイルサーバーの中にNASが含まれる、というのがイメージできるとよいでしょう。
ファイルサーバーとNASのメリット・デメリット
まずは、ファイルサーバーとNASの定義について以下の通りとして話を進めさせていただきます。
- NASで作っていないファイル共有システム=ファイルサーバー
- NASで作ったファイル共有システム=NAS
として説明していきます。
ファイルサーバーのメリット・デメリット
ファイルサーバーのメリット・デメリットは次の通りです。
ファイルサーバーのメリット
ファイルサーバーのメリットは
- 構築・機能の選択肢が多い
- セキュリティ柔軟性が高い
- 容量拡張の柔軟性が高い
です。
ファイルサーバーを作る際は、さまざまな構築方法を試すことができます。自社の規模が小さければ無料のクラウドストレージを、セキュリティを重視するならばオンプレミス型にするといった選択肢が多いので自社に適した方法でファイルを共有しやすいです。機能も後で拡張できるので、会社の成長に合わせて変更可能になっています。
またセキュリティの柔軟性が高いのもメリットになります。NASでもアクセス権限の設定などはできますが、ファイルサーバーにはNASと違ってセキュリティ設定の限界があまりありません。指定したIPアドレスからのアクセスを遮断する、VPN接続のみ許可するといった設定も可能で高いセキュリティ性を実現可能です。
さらに容量拡張にも限界がありません。オンプレミスでもストレージを追加して認識させれば容量を増やせますし、クラウド型では契約プランのアップグレードで容量が増えていくので必要ボリュームが増加しても安心です。
ファイルサーバーのデメリット
ファイルサーバーのデメリットは
- 構築するには専門的なスキルが必要なケースがある
- コストが高くなってしまう場合がある
です。
たとえばレンタルサーバをベースにインターネットから使えるファイルサーバーを構築する場合、パソコンからファイルを操作する際FTPソフトウェアが必要になってきます。ソフトウェアによってはアクセス権限の設定などがややこしくなっているケースがありますし、操作を間違えるとファイルを間違えて消してしまうといったリスクを発生させてしまう可能性があるでしょう。そのため、社内に専門的な知識を持った担当者またはアウトトーシング先の協力が必要になります。
またオンプレミスでは初期導入費が高くなったり、クラウド型では継続費用がかさんでくる、さらには運用保守するための人件費といったコスト面でのデメリットがあるのも忘れてはいけません。
NASのメリット・デメリット
NASのメリット・デメリットは次の通りです。
NASのメリット
NASのメリットは
- 設定が容易で専門的な知識がなくても設置可能
- コストを抑えやすい
- 処理性能が高くなりやすい
などです。
NASはデータの保存・管理などに特化したファイル共有システムを作るために使います。ですから基本設定を行えばすぐに使えるようになりますし、手間が掛かりません。オンプレミスといったファイルサーバーの構築に自信のない方はNASがおすすめです。
また買い切りで済む場合が多いので、コストが初期投資のみで抑えられるのもNASのデメリットです。初期投資を抑えたい方もNASの構築を考えてみるとよいでしょう。
さらにデータの取り出しなどにも最適化されているので、高速に読み書きができるといったメリットもあります。たとえばレンタルサーバ上にファイルサーバーを構築した場合、選んだレンタルサーバがファイルサーバーに適しておらず読み書きが遅い、といったデメリットが出てくるケースがあります。そういったファイルサーバーと比較すると、NASでシステムを構築したほうがメリットを感じられるかもしれません。
NASのデメリット
NASのデメリットは
- 機能のカスタマイズができない
- 拡張・増設が難しい
- 容量拡張が難しい
です。
NASではできあいの管理ソフトから設定を操作するので、細かい権限を設定したりといった機能の拡張が難しいケースがあります。また容量拡張・増設が難しいのもデメリットです。ストレージ換装で対応はできますが、増設できる容量には限界があります。
たとえばクラウドストレージだと容量カスタマイズが簡単にできますし、容量上限にも幅があります。そういった点を考えると容量拡張が限定的になるのはデメリットとなるでしょう。
会社で扱うデータ規模が将来的にそこまで増えないだろう、といった場面、またいくつかあるファイル共有システムの1つとして検討する場合などはNASが選択肢になってきます。
ファイルサーバーとNAS!選択する際のポイントとは

ファイルサーバーとNAS、それぞれの選び方のポイントをまとめてご紹介します。
サーバーの利用目的を考える
まずはサーバの利用目的を考えます。
- 将来性を考えてカスタマイズ性能が高い機器にしたい:オンプレミスのファイルサーバー
- シンプルに設定して社内に設置したい:NAS
といったように、目的に応じて選ぶべき構築方法は変わってきます。
コストを抑えながら共有の利便性を損なわないようにするためには、目的意識を持ってファイル共有システムを選ぶ必要があるでしょう。
容量とコストの兼ね合いを考える
ストレージ容量とコストの兼ね合いを考えるのも重要です。
NASを使用しないケースのファイルサーバーでも、NASであっても、ストレージ容量が増えれば価格は高くなりますが容量に対する価格の上がり具合が鈍ってきます。大容量を使う予定が今後ある場合は、最初から多めの容量を使える構築方法を利用したほうがコスト面でも安心です。
また将来的にどのくらいストレージ容量が追加で必要になってくるかも考えて、コストが安く抑えられるファイル共有システムを構築できるとより安心できるでしょう。
ただし、クラウドサービスを活用したファイルサーバーを構築する場合は、注意が必要です。
例えば、動画を大量に扱っていたり、高解像度の写真やCADデータなど容量の大きなファイルを大量に扱っている場合は、ファイルのアップロード、ダウンロード時の通信量に応じても課金されてしまうものも多いので、クラウドサービスのコストが大きくなってしまいます。
またDropboxやBoxなどのようなオンラインストレージはユーザー数で課金されるサービスも多いので注意が必要です。
長期でみると、オンプレミスのファイルサーバーやNASのほうがコストを抑えられる可能性が高くなるので、トレンドをおってクラウドサービスにファイルサーバーを安易に移管してしまうのは避けたほうが良いでしょう。
よく勘違いをしてしまうのは、クラウドサービスは初期費用が抑えられ、月額制となる場合が多いので、コストを軽減できると思う担当者が非常に多いようです。
しかし、長期的に考えると、間違いなくクラウドサービスのほうがコストが多くかかります。
急激にストレージの費用が下がってきているクラウドサービスですが、まだまだオンプレミスと比較しても、クラウドサービスのストレージコストは大きいのです。
ファイルサーバーをクラウド化するメリットについてははこちらの記事をご参考ください。「ファイルサーバーをクラウド化するメリットとコストの変化について」
独自機能を比較する
ファイルサーバー・NASは差別化するために、独自の便利な機能が搭載されているケースがあります。たとえばGoogleドライブだと、GmailといったGoogleサービスと連携してファイル管理、共有できる機能が利用可能といったようなケースがあります。
自社で使っているサービスとの連携性なども考えて、独自機能面も含めて自社環境に最適なファイル共有システムを選ぶとよいでしょう。
中小企業の最適なファイルサーバー環境構築ならITボランチ
ファイルサーバーなら自由度も高く、拡張性もありますので、業務効率化や生産性の向上といった面でもお役立ちするものと思われます。しかし、中小企業では専任の情シス・社内SEといったIT担当者を雇用することが人件費との兼ね合いからも難しいケースも多く、ファイルサーバーの設置及び運用をするだけのスキルを持ち合わせていない担当者が設置されてしまうケースが多いのです。
そうすると外部ベンダーの言われたまま、機器やソフトを導入してしまったり、高い保守費用がかかり続けていたりと最適な環境とは言い難い状態な中小企業を非常に多く目にします。
大切なのは、ファイルサーバー、NASのメリットやデメリットを理解した上で自社に最適なツールを選定することです。一番リスクが高いのは、従業員のパソコンのローカルストレージにしかデータが保存されていない状況ですので、従業員への教育を徹底し、基本的に業務データはフィルサーバに保管することを徹底しましょう。
また、オンプレミスのファイルサーバーからクラウドストレージに移管したいというご相談も急激に増えております。しかし多くの中小企業様はクラウドストレージへ移管することでコストを下げられると誤解されているケースが目立ちますが、本来クラウドストレージを活用することはコスト面が優れているからだけではないのです。それぞれのメリットやデメリットなどを加味して検討することをおすすめいたします。
IT保守サービスを展開しておりますITボランチでは、これまで400社以上のIT環境に関する対応をしてきた実績がございます。ご相談は無料でご対応いたしますので、自社のIT環境にお困りごとや、実現したいことがあれば、まずはお気軽にご相談ください。