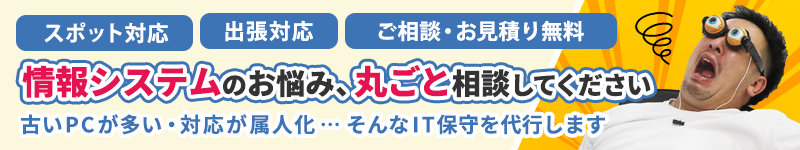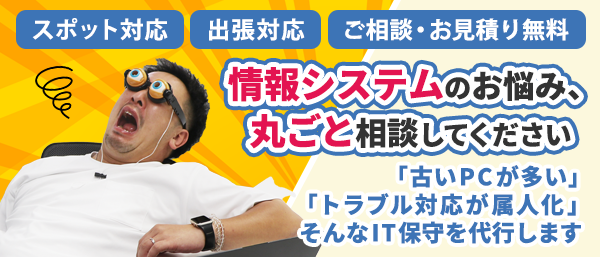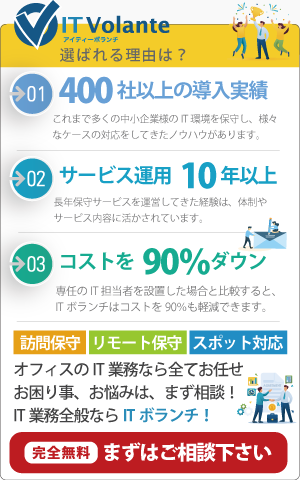シャドーITという言葉を聞いたことはないでしょうか。
働き方改革の推進、2020年以降の新型コロナウィルス感染防止対策によるテレワークの普及により私たちの働く環境は一変しました。テレワークの導入が急加速することで、コミュニケーションツールの導入、クラウドサービスの利用促進など、ITを取り巻く環境も大きく変容しています。
本記事では、シャドーITの概要、リスク、発生する原因、よく使われるツールやサービス、そして有効な対策方法までを詳しく解説します。従業員の利便性を損なわず、かつ安全に業務を遂行するためのヒントとしてお役立てください。
IT業務のお悩みやお困りごと、コスト削減をお考えなら、まずはITのことならなんでも無料で相談できるITボランチへご相談ください。お問い合わせはこちらから
Contents
シャドーITとは
シャドーITとは、従業員が業務で使用するIT機器やサービスのうち、企業が把握していないものを指します。これは、企業が許可していないPCンやスマートフォン、クラウドサービス、チャットツールなどを、従業員が自己判断で業務に利用してしまう状況です。
正式な承認を経ていないため、企業のセキュリティポリシーや運用ルールの対象外となり、管理が困難になります。その結果、情報漏えいや不正アクセスなどのリスクが高まります。
シャドーITとBYODの違い
シャドーITと混同されやすいのが「BYOD(BringYourOwnDevice)」です。BYODとは、従業員が私物のデバイスやサービスを業務に利用することを企業が承認し、一定のルールのもとで運用する仕組みです。
一方、シャドーITは企業が承認していないため、セキュリティ管理が行われず、予期せぬトラブルに発展する危険性があります。

シャドーITはなぜ問題なのか?
シャドーITが大きな問題となるのは、企業が把握・管理できないIT機器やサービスが業務に混ざり込むことで、セキュリティや業務品質に影響を与えるからです。
通常、企業が導入する業務用システムやデバイスは、情報システム部門や管理部門がセキュリティ評価を行い、安全性を確認したうえで利用が許可されます。しかし、シャドーITはその承認プロセスを経ていないため、以下のような問題が発生します。
- 管理者が存在しない
管理責任者がいないため、セキュリティ設定や利用状況の監視が行われず、リスクが放置されます。 - 脆弱性への対応が遅れる
無許可ツールで脆弱性が見つかっても、企業は存在自体を知らないため、パッチ適用や利用停止などの対策ができません。 - コンプライアンス違反の可能性
個人情報保護法や業界ごとのセキュリティ基準(例:金融機関のFISC安全対策基準)に違反し、罰則や信用失墜を招く恐れがあります。 - 予期せぬコスト発生
無許可サービスに保存されたデータが流出し、事故対応や補償に多額のコストがかかる場合があります。
特に近年は、クラウドサービスや外部アプリが容易に利用できるようになったことで、従業員が便利さを優先してシャドーITを使うケースが急増しています。その結果、企業が気づかないうちに重大なセキュリティリスクを抱え込んでしまうのです。
シャドーITによるセキュリティリスク
シャドーITは見えない場所で運用されるため、セキュリティ事故の発生率が高くなります。代表的なリスクを以下に詳しく解説します。
情報漏えい
シャドーITによる最大のリスクが情報漏えいです。
例えば、従業員が私物のクラウドストレージ(GoogleドライブやDropboxなど)に機密ファイルをアップロードすると、アクセス権限の設定ミスやアカウントの乗っ取りにより、外部にデータが流出する危険があります。
特に個人情報や契約書、顧客リストなどが漏れると、取引先からの信頼低下や損害賠償請求につながる恐れがあります。
不正アクセス
承認されていないアプリや外部サービスは、パスワード管理や暗号化が不十分な場合が多く、第三者からの不正アクセスを受けやすくなります。
一度侵入されると、情報の盗み見だけでなく、端末の遠隔操作や盗聴など、物理的な被害にまで発展する可能性があります。
マルウェア感染
無許可のアプリやフリーソフトは、公式ストアを経由していない場合や、開発元のセキュリティ対策が不十分な場合があり、マルウェア感染のリスクがあります。
感染すると、ファイルの暗号化による身代金要求(ランサムウェア被害)や、社内ネットワーク全体への拡散が起こり、全社的な業務停止を引き起こす可能性があります。
アカウントの乗っ取り
無許可サービスを利用する際、業務用と同じパスワードを使い回してしまうケースがあります。
もしそのサービスが情報漏えいを起こすと、攻撃者は同じパスワードで社内システムに不正ログインし、メールやチャットの内容、顧客情報などを盗むことができます。
端末の紛失
私物スマートフォンやノートPCを業務利用している場合、端末を紛失しても企業は遠隔ロックやデータ消去ができません。
特に、電車やカフェでの置き忘れなど日常的に起こり得るミスが、重大な情報漏えい事故に直結します。実際、多くの企業で発生している情報漏えい原因の上位は「置き忘れ・紛失」です。

シャドーITが生まれる原因
シャドーITは、単に従業員のルール違反というだけではなく、業務環境や企業文化、ITの使い勝手など、さまざまな要因が複合的に絡み合って発生します。主な原因は以下の通りです。
従業員が不便に感じている
企業で承認されているデバイスやアプリが、実務のスピード感や利便性に合わない場合、従業員は自分でより使いやすいツールを探してしまいます。
たとえば、
- 社内承認のファイル共有システムが遅くて使いにくい
- 承認チャットツールが外出先からアクセスしづらい
- 権限申請に時間がかかりすぎる
といった状況が続くと、GoogleドライブやLINEなど、即使える外部サービスに流れる傾向が強まります。
働く場所が多様化している
テレワークや出張、コワーキングスペースなど、働く場所がオフィス外に広がると、社内ネットワークやIT資産の一元管理が難しくなります。
外出先で急ぎの作業が必要になった場合、
- 個人スマホで資料を送る
- 公共Wi-Fiでクラウドにアクセスする
- 家のPCから社内システムに接続する
といった行為が増え、結果的にシャドーITの温床になります。
そもそもリスクを理解していない
多くの従業員は、「便利だから使っているだけ」で、それがセキュリティ上どれほど危険かを認識していません。
また、経営層や管理部門もシャドーITの現状やリスクを把握しておらず、具体的な対策や啓発活動が行われないまま放置されるケースもあります。
「知らないうちにルール違反」という構造が、シャドーITを長期化させる原因です。
シャドーITが発生しやすいツール・サービス
シャドーITは、特定のジャンルのツールやサービスで特に発生しやすい傾向があります。以下は代表例です。
私物のデバイス(スマホやPCなど)
私用スマホやノートPCを社内ネットワークに接続すると、企業側はセキュリティ状態や利用履歴を把握できません。
例えば、ウイルス対策ソフトが入っていない端末から接続すれば、マルウェア感染や不正アクセスのリスクが一気に高まります。
チャットツール(LINEやSlackなど)
業務連絡を私用チャットアプリで行うと、企業が会話内容を監査できず、端末を紛失しただけで大量の社内情報が外部に流出する恐れがあります。
また、履歴が外部サーバーに残り続けるため、過去の情報もリスク対象になります。
フリーメール(GmailやYahoo!メールなど)
私用メールアカウントから業務連絡を行うと、メールの誤送信や迷惑メールへの振り分け、検索性の低下など、業務効率と安全性の両面で問題が発生します。
特に、重要書類を誤って第三者に送信した場合、情報漏えい事故として重大な損害を生む可能性があります。
クラウドストレージ(DropboxやGoogleドライブなど)
便利な反面、アクセス権限の設定ミスや共有リンクの流出により、外部から誰でも閲覧できる状態になるケースがあります。
一度公開されてしまった情報は完全な回収が難しく、特に機密資料や顧客データは深刻な被害につながります。
フリーWi-Fi
空港やカフェのフリーWi-Fiは暗号化が不十分な場合が多く、通信内容を第三者に傍受されるリスクがあります。
社内システムやクラウドへのログイン情報が盗まれれば、企業全体のセキュリティが危険にさらされます。

シャドーITをなくす対策
シャドーITを根絶するためには、単に禁止するだけでは不十分です。便利さと安全性を両立できる仕組み作りが重要です。
シャドーITを使わなくてもよい環境を整える
公式に承認されたツールやデバイスでも、スピード・使いやすさ・機能面で従業員が満足できるよう改善します。
例えば、
- 高速で安定したVPN環境の整備
- 外出先からも利用可能な公式クラウドサービスの提供
- モバイル端末用の業務アプリの導入
など、従業員が「正規ツールの方が便利」と思える環境が理想です。
ガイドラインを策定し、社員教育する
シャドーITの危険性、禁止事項、違反時の影響などを明文化したガイドラインを作成し、全社員に周知します。
年に一度のセキュリティ研修や、実際の被害事例を交えた勉強会なども効果的です。
シャドーITを認める「BYOD」を検討する
「BringYourOwnDevice(私物端末の業務利用)」を認めつつ、セキュリティ管理を企業側で行う方法です。
MDM(モバイルデバイス管理)ツールを活用し、端末のセキュリティ設定や遠隔ロックを行える体制を整えれば、従業員の利便性と安全性を両立できます。
アクセス管理ツールを導入する
クラウドや社内システムへのアクセスを一元的に監視・制御できるツールを導入します。
異常なログイン試行や深夜のアクセスなどを検知し、早期対応できるようにすることで、不正利用や情報漏えいを未然に防ぎます。
企業はシャドーITのリスクを理解し適切な対策が求められる
シャドーITは従業員の利便性と引き換えに、企業へ深刻なリスクをもたらします。重要なのは、従業員が安心して業務を遂行できる環境を整備しつつ、セキュリティを確保することです。ガイドライン策定やツール整備、社員教育を組み合わせることで、シャドーITを抑止し、安全な業務環境を維持できます。