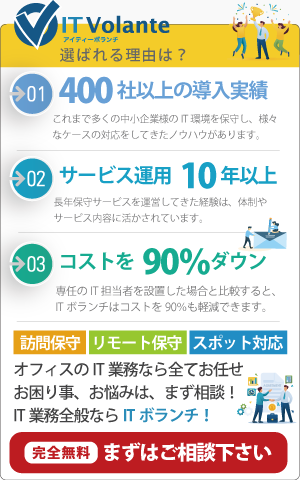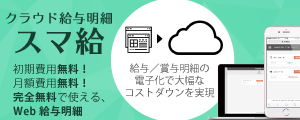近年、サーバー環境はオンプレミス型からクラウド化へシフトしています。
多くの企業はクラウド化を検討していますが、正確に理解した上で検討を進めていない場合は正しい判断になっていない可能性もあります。
この記事では、クラウド化のメリット・デメリットから実施の手順と注意点などを紹介していきます。
□■□■IT業務のお悩みやお困りごと、コスト削減をお考えなら、解決手段があるはず!まずはITボランチへご相談(無料)ください。無料でのご相談はこちらから□■□■
クラウド化とは
近年、ビジネスにおいてシステム環境を構築する際に最初に検討されるのが「クラウド(クラウド・コンピューティング)」です。
クラウドとは、クラウドサービス事業者が提供するサーバやシステムを、インターネットやVPN、専用線などのネットワークを介して利用し、使用分に応じて料金を支払うサービスのことです。
クラウド環境には様々な種類があり、課題や業務特性に合わせて選択する必要があります。
「クラウド化」とは、既存のオンプレミスで利用されていたシステムをクラウドサービスに移行することを指します。
具体的には、オンプレミスで利用していたアプリケーションをパブリッククラウド上のシステム基盤に移行したり、クラウドサービス事業者の提供するWebサービス製品に切り替えたりする方法があります。
クラウドといえば、セキュアな独自環境を構築できるプライベートクラウドより環境を共同で利用するパブリッククラウドを利用するのがコストも抑えることができ、メンテナンスも複雑化しないこととからも一般的です。
クラウド化によって、機器の調達や保守・メンテナンスを気にすることなく、利用者は簡単な操作でサーバやシステムを利用できるようになります。
これにより、企業や利用者にとって大きなメリットが生まれるのです。
クラウド化の3つの種類
クラウドサービスには、大きく分けてSaaS/PaaS/IaaSの種類があります。クラウド化の際には、どの種類のサービスに移行するべきかを念頭にシステム構成を検討する必要があります。
ここでは、それぞれのクラウドサービスを利用したクラウド化について解説していきましょう。
SaaSを導入してアプリケーションのクラウド化
SaaS(サース:Software as a Service)とは、クラウドサービス事業者が提供するアプリケーションを利用できるサービスです。
例えば、PCにインストールして利用していたメールソフトを、ブラウザからアクセスできるWebメールに切り替えることが挙げられます。
クラウドサービス事業者が開発したアプリケーションを利用するため、大きくカスタマイズするような使い方は想定されていませんが、元々用意されている機能で要件を満たせる場合には、有用なクラウド化の手段です。
PaaSを導入してプラットフォーム環境のクラウド化
PaaS(パース:Platform as a Service)とは、プログラムを動かすことのできるプラットフォーム(ミドルウェア)を利用できるサービスです。
PaaSを利用したクラウド化では、オンプレミスで利用していたデータベース製品やアプリケーションサーバ製品を、PaaSで提供されているサービスに切り替えてシステムを構築することになります。
PaaS上で動作するアプリケーションは利用者が自由に開発することができます。SaaSよりもカスタマイズできる範囲が広いことが、PaaSを利用したクラウド化の大きな特徴です。
IaaSを導入して社内インフラのクラウド化
IaaS(イアース:Infrastructure as a Service)とは、仮想化技術を利用して、サーバなどのハードウェアリソース(CPU/メモリ/ストレージ)を利用できるサービスです。
IaaSを導入すると、オンプレミスで運用していたインフラ機能をクラウドサービス上に構築できるようになります。例えば、自社のデータセンタで構築していたサーバをクラウド化すれば、自社内にハードウェア機器を置く必要がなくなり、ハードウェアのメンテナンスからは解放されます。
サーバは自由にカスタマイズできるため、利用者が自由にミドルウェアをインストールしたり、自社で開発したアプリケーションを搭載したりすることができます。
代表的なサービスとしてすでに多くの企業が利用しているAmazonのAWS、MicrosoftのAzure、GoogleのGCPがあります。
IaaSは、SaaSやPaaSで提供されているサービスでは必要な機能を満たせない場合に、より自由にシステム構築ができる形として提供されています。
これまでオンプレミスで自社サーバーを設置していた企業がIaaSでクラウド化にシフトする流れが急増しています。これは、リモートワークなどが増えたことにより、社内サーバーを持つことのメリットが減ったこと、パブリッククラウドのコストが下がったことなどが理由として考えられます。
クラウド化をするメリット・デメリット
なぜ多くの企業でクラウド化が進んでいるのでしょうか。
これほどの勢いで利用者が広がっているには明確な理由があります。ただ、クラウド化には大きなメリットがある反面、デメリットも存在しています。
ここでは、そのメリット・デメリットについて説明していきましょう。
クラウド化のメリット
コスト削減が可能
システムを構築・保守していくためには、多大な費用が必要になります。
サーバやネットワーク機器を設置するためのデータセンタの利用費用に始まり、ハードウェアの導入などの初期費用がかかります。
運用フェーズに入ってからも、ハードウェア故障対応やOS・ミドルウェアのパッチ当て、機器もしくはソフトウェアの保守切れに伴うリプレース作業など、多くの人手や費用が必要になります。
クラウドサービスは、クラウドサービス事業者のシステムリソースを間借りして、使った分だけ利用料を支払う課金体系となっています。
莫大な初期費用は不要な上、ハードウェアの保守切れにより数年ごとに訪れていたリプレース作業も必要なくなるため、大きなコスト削減効果が期待できます。
運用管理・メンテナンスの負担削減できる
オンプレミス環境の運用では、自社に設置されたハードウェア機器の保守・運用管理のために専任スタッフが必要になります。
クラウド化により、少なくともハードウェア機器の運用はクラウドサービス事業者に任せられるため、管理やメンテナンスの手間が削減できます。
また、PaaSやSaaSを選択すれば、さらにソフトウェアのアップデートなどのメンテナンスが削減できます。
メンテナンスの手間が軽減できることにより、専任スタッフの保守工数が削減できますので、人的リソース面でも負担が減らせるというメリットがあります。
スケール変更(拡張・縮小)が容易にできる
クラウドを利用すると、サーバやミドルウェアスペックのスケール変更が容易になります。
需要の変動に柔軟に対応でき、負荷が増えた時にはリソースを追加し、必要がなくなれば削減できます。
これにより、業務の変更やサービスの成長に合わせてシステムのパフォーマンスを維持しながら、運用コストを最適化することができます。
BCP対策が可能
データセンタ障害や自然災害の際でも事業の継続を可能とするBCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)の策定は、多くの企業で大きな課題となっています。
オンプレミス環境でBCP対策を行う場合は、データセンタを2拠点以上用意する必要がありますし、設置する機器もデータセンタの数だけ揃える必要があります。
有事の際にしか利用されないBCP用のデータセンタを保持・運営するのは、企業にとって大きな負担です。
クラウドサービスの多くは多拠点化されており、簡易な設定でデータやシステム設定等の遠隔地保管ができるため、クラウド化によって容易にBCP対策が可能となります。
アクセスがしやすくなる
クラウド環境では、インターネットを介してアクセスするため、場所やデバイスに依存せずにアプリケーションやデータにアクセスできます。
従来のオンプレミス環境では、特定の場所や特定のデバイスからのみアクセスできるという制約がありましたが、クラウドを利用することで、インターネット接続さえあればどこからでもアクセスできるようになるため、リモートワークなど働き方改革ができる環境が構築しやすいのもポイントです。
クラウド化のデメリット
カスタマイズに制限がある
クラウド環境では、提供された機能や設定にとどまり、アプリケーションやサービスのカスタマイズが制限されます。
特定のニーズに完全に合わせることが難しく、ビジネスの要件に合わない場合があります。
ベンダー依存のリスクがある
クラウドサービスを提供するベンダに依存することで、そのベンダがサービスを変更または終了した場合、ビジネスに影響を及ぼすリスクがあります。
サービス変更や終了に伴うデータの移行やシステムの再構築にかかるコストや時間を考慮する必要があります。
クラウド化を実施する手順
さまざまなメリットがあるクラウド化ですが、無事に移行を成功させるには事前に様々な検討をする必要があります。
ここでは、クラウド化を成功させるために必要な流れや進め方について確認していきたいと思います。
1.自社の課題を明確し、クラウド化する範囲を決める
クラウド化を検討する前に、まずシステムに関する自社の課題や問題点を明確にしておく必要があります。
システムの運営コストが負担になっている、業務を改善するための機能が現状のシステム環境では実現できない、システム構築作業に時間がかかっているなど、企業によって様々な課題が存在しているはずです。
多くの場合、それらの課題の解決にクラウド化は有効です。
ただし、対象システムのすべてをクラウド化しない方がよいケースも考えられます。課題や問題点によってクラウド化の適用範囲は変わってきます。
既存のオンプレミス環境とクラウドを連携させるハイブリッドクラウドが有効なケースもあるでしょうし、すべてクラウド化した方が良いケースもあるでしょう。ひょっとすると、クラウド化しなくとも課題が解決できる場合もあるかもしれません。
クラウド化することが目的となってしまわないよう、課題の解決を念頭にクラウド化する範囲を決めていきます。
2.社内運用ルールやセキュリティポリシーを確認する
クラウド化では、クラウドサービス事業者のデータセンタを利用することになるため、自社の社内運用ルールやセキュリティポリシーと適合しないケースも起こり得ます。
通常、クラウドサービスのデータセンタの所在地は明らかにされておらず、利用者側のシステム監査の受け入れやデータセンタの視察には対応できない場合があります。
また、クラウドサービスでシステムを構築する際に、海外のリージョンを選択してしまうと、日本の法律が適用されず社内のセキュリティポリシーに抵触してしまうケースも考えられます。
あらかじめ自社のシステム運用ルールやセキュリティポリシーなどを確認し、クラウド化という手段と適合しているかを確認しておきましょう。
3.クラウド化に利用するサービスを選ぶ
クラウドサービス事業者や製品にも、いくつかの種類があります。
クラウドサービス事業者によって、それぞれの特色は異なりますし、利用料金も異なります。クラウド化する目的、目標、範囲から自社にとって最適なサービスを選定することが大切です。
複数のクラウドサービスを比較検討して、最適なサービスを見極める必要があります。
4.小規模なクラウド化から始める
クラウド化には大きなメリットがありますが、規模の大きなシステムを一度に移行するにはリスクが伴います。
業務システムをクラウド化する前に、PoC(Proof of Concept:概念実証)を行い、想定通りに移行が可能かどうか検証を行いましょう。
また、PoCが問題なかった場合であっても、最初は比較的規模の小さなシステムや機能からスモールスタートし、効果の検証と改善を繰り返しながらクラウド化の範囲を広げていくことが大切です。
5.改善を繰り返しながら運用・効果を検証する
一定の期間クラウドを利用した後、費用対効果の検証を実施します。
想定通りの効果が得られているのか、もし得られていないのであればどの部分に問題があるのかを確認します。
問題のある部分は改善する必要がありますし、検証結果によってはクラウド化する範囲や対象を変更していかなければいけないかもしれません。
問題がある部分の改善を行いながら、どのようにクラウド化を拡大していくのが効率的かつ効果的なのか情報を整理していきましょう。
クラウドサービスは柔軟に拡張や縮小ができるため、実際に運用しながら計画を見直していくことも重要です。
PDCAサイクルを回し続けることで、より良いクラウド環境の構築を目指していきましょう。
クラウド化を実施するときの注意点
既存システムと合わない場合もある
クラウド化を実施する際には、既存のシステムとの整合性に注意が必要です。
一部のシステムはクラウド環境に移行することが難しく、互換性の問題が発生することがあります。
特に、レガシーシステムや特定の業務に特化したシステムでは、クラウド化が適切でない場合もあります。
事前に十分な検討と評価を行い、クラウド化の可否を判断することが重要です。
コストが増えてしまうケースもある
クラウド化を実施する場合、初期投資やランニングコストが増加する可能性があります。
特に、クラウドサービスやクラウドサーバーの利用料やデータ転送料、追加機能の料金などが考慮される必要があります。
また、システムの移行やデータの変換にかかる費用も加味されるべきです。
綿密なコスト分析を行い、将来的な負担を見据えた上でクラウド化を進めることが重要です。
例えば、大容量のデータを扱っているようなファイルサーバーをクラウド化するような場合、逆にコストが増えてしまうことも考えられます。
情報セキュリティ対策は必要
クラウド化を実施する場合、情報セキュリティ対策が重要です。
クラウド環境では、データが第三者の管理下に置かれるため、セキュリティリスクが増大します。
適切なアクセス管理、データ暗号化、セキュリティポリシーの実施など、十分なセキュリティ対策が必要です。
また、クラウドプロバイダのセキュリティ対策やコンプライアンス状況も確認し、信頼性の高いパートナーを選定することが重要です。
クラウド化が必要かお悩みならITボランチに相談
今回は、クラウド化についてご紹介しました。
クラウド化は、効率化や柔軟性をもたらす一方で、適切な計画と対策が欠かせません。
メリットを享受するためには、デメリットやリスクも理解し、適切な手順と注意を踏まえて実施することが不可欠です。
ITボランチサービスでは、社内IT担当者(情シス・社内SE)というスタンスで、貴社のシステム環境を把握し、IT関連業務を包括してサポート致します。
クラウド化の専門知識を持ったSEによる迅速で適切な対応が可能です。
クラウド化が必要かお悩みなら、ぜひITボランチにご相談ください。初回のご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。