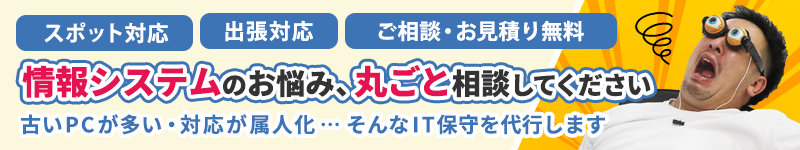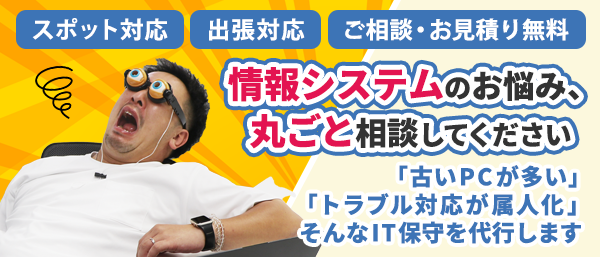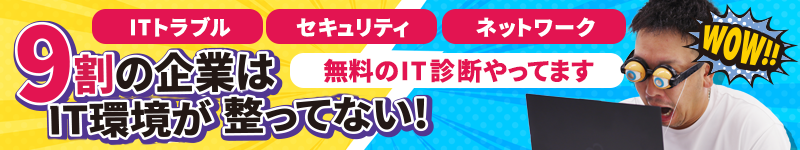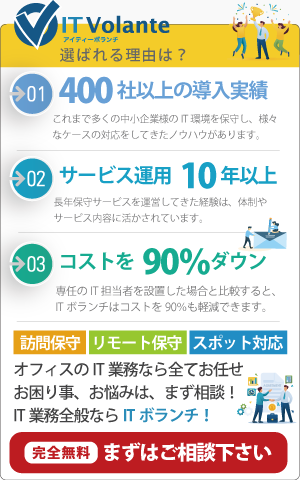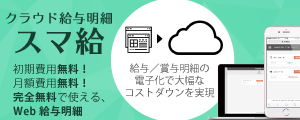2025年10月14日、Windows10のサポートがついに終了します。多くの企業でまだ利用されているWindows10ですが、サポート終了後も使い続けることには大きなリスクがあります。特に、会社に専任の情報システム部門がなく、OSやセキュリティに詳しくない担当者の方にとっては「何をどう準備すればよいのか分からない」という不安も多いのではないでしょうか。
本記事では、「Windows10サポート終了後に何が起こるのか」「どんなリスクがあるのか」「どのような対応が必要か」をわかりやすく解説します。さらに、アップグレード作業を効率的に進めるための方法や、情報システム部門の負担を軽減するアウトソーシングの活用についてもご紹介します。
□■□■IT関連の問題解決や、コスト削減の方法について、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひITボランチにご相談ください。無料でのご相談はこちらから□■□■
Contents
Windows10は2025年10月14日にサポート終了
Windows10は2015年に登場し、多くの企業で標準OSとして利用されてきました。しかし、マイクロソフトはVersion22H2を最終バージョンと定め、サポート終了日を2025年10月14日と発表しています。
つまり、2025年10月14日以降はWindows10に対して更新プログラムやセキュリティパッチの提供が一切行われなくなるということです。
現在も多くの企業がWindows10を利用していますが、対応を先延ばしにすると、社内システムや業務に深刻な影響が出る可能性があります。
Windows10サポート終了後も使い続けるとどうなるのか
サポートが終了した後でも、Windows10のパソコン自体は起動し、通常通り使用できます。インターネットに接続して検索したり、ExcelやWordを開いたりすることも可能です。
しかし大きな問題は、マイクロソフトから更新プログラムやセキュリティパッチが提供されなくなることにあります。これは「新しい脅威に対して無防備になる」という意味です。業務で利用している企業にとっては、セキュリティ事故や業務停止につながる重大なリスクを抱えることになります。
サポート終了後にWindows10を使い続けるリスク
サポート終了後のWindows10は、時間の経過とともにサイバー攻撃の標的になりやすくなります。攻撃者は、サポートの切れたOSの既知の脆弱性を狙って攻撃を仕掛けてくるためです。
例えば、メールに添付された不正ファイルを開いた瞬間にウイルスが侵入し、社内ネットワーク全体に拡散するケースも想定されます。
また、脆弱性が新たに発見されても、マイクロソフトから修正プログラムが提供されないため、防御手段がありません。これは「建物の鍵が壊れても修理してもらえず、そのまま放置している」状態に例えられます。
特に企業利用では、取引先や顧客の情報漏えいに直結するため、1台のパソコンのリスクが全社的な問題に発展する可能性があります。
アプリが使えなくなり業務に支障が出る
もうひとつの大きなリスクは、業務で利用しているアプリケーションやソフトウェアが動作しなくなる可能性です。
多くのソフトウェアベンダーは「サポートが終了したOSでの動作保証」を打ち切ります。これにより、以下のようなトラブルが発生する恐れがあります。
- 会計ソフトや販売管理システムがアップデートできなくなる
- インターネットバンキングやクラウドサービスが利用不可になる
- Webブラウザやメールソフトが最新バージョンに更新できず、セキュリティ上の脆弱性を抱える
これらは単なる使い勝手の問題にとどまらず、請求業務や給与計算といった会社の根幹業務に直接影響を与えることもあり得ます。最悪の場合、業務の停止や納期遅延といった重大なトラブルにつながりかねません。
法令遵守ができなくなる可能性
さらに見落としがちなのが、法令遵守や取引先からの信頼への影響です。
情報セキュリティに関する法律や規制では、常に最新のセキュリティ対策を講じることが求められます。サポート切れのOSを使い続けることは、事実上「脆弱性を放置している状態」であり、個人情報保護法やISMS認証などの基準に抵触する可能性があります。
例えば、顧客情報が漏えいした場合、法令違反による行政指導や罰金だけでなく、取引停止やブランドイメージの失墜といった企業活動全体への打撃につながることも考えられます。
また、近年は取引先企業からセキュリティチェックを受けるケースが増えています。その際に「サポート切れOSを利用している」と判定されれば、新規取引のチャンスを逃すリスクも高まります。
Windows10のサポート終了に向けて必要な対応
こうしたリスクを避けるためには、早めに移行の準備を進めることが重要です。主な選択肢は以下の3つです。
Windows11へアップグレードする
現在利用中のPCがWindows11のシステム要件を満たしていれば、OSをアップグレードするのが最も効率的です。費用を抑えながらセキュリティを確保でき、業務の継続性も守れます。
Windows11へ買い替える
古いPCの場合は、アップグレードに対応できないケースが多いため、新しいPCへの買い替えが必要です。新機種は性能やセキュリティ機能が強化されており、今後数年の安定運用が見込めます。
セキュリティ対策をしてWindows10を使い続ける
業務システムの都合などでどうしてもWindows10を残す場合は、セキュリティソフトやネットワークの多層防御を強化する必要があります。ただしこれは一時的な延命措置であり、根本的な解決にはなりません。できる限り早期に移行計画を立てることが求められます。
Windows11へアップグレードする方法と注意点
Windows11へのアップグレードは、企業にとって避けて通れない作業です。しかし、手順を誤ったり準備を怠ったりすると、業務データの消失やアプリケーションの不具合など、深刻なトラブルを招く可能性があります。ここでは、安全かつスムーズに移行を進めるための手順と注意点を解説します。
システム要件を確認する
まず最初に確認すべきは、現在利用しているPCがWindows11のシステム要件を満たしているかどうかです。要件を満たしていないPCにはインストールできないため、事前確認は必須です。
Windows11の主な要件は以下の通りです。
- CPU:1GHz以上、2コア以上の64ビット対応プロセッサ(Intel第8世代以降、AMDRyzen2000シリーズ以降など)
- メモリ:4GB以上(推奨8GB以上)
- ストレージ:64GB以上
- TPM:TrustedPlatformModule(TPM)バージョン2.0
- セキュアブート:有効化されている必要あり
マイクロソフトが提供する「PC正常性チェック」アプリを使えば、自動的に要件を満たしているか判定できます。特に、TPM2.0やセキュアブートの設定はBIOSで変更が必要な場合もあるため、担当者が戸惑いやすいポイントです。
データをバックアップする
アップグレード作業を始める前に、必ず重要なデータをバックアップしましょう。
外付けHDDやSSD、社内NAS、クラウドストレージ(OneDriveやGoogleDriveなど)を活用すると安全です。
特に以下のデータはバックアップ対象に含めることをおすすめします。
- 顧客リストや営業資料
- 会計データや請求書ファイル
- 業務で利用するアプリケーションの設定ファイル
- メールの送受信履歴
バックアップを怠ると、アップグレード中の不具合や停電などでOSが起動しなくなった場合に、業務データを失う危険があります。
アップグレードを実行する
準備が整ったら、実際にアップグレードを開始します。手順は次の通りです。
- Windowsボタンをクリック
- 設定>更新とセキュリティ>WindowsUpdateを選択
- 「Windows11へのアップグレードの準備ができました」と表示されていれば、「ダウンロードしてインストール」をクリック
- 使用条件を確認後、「同意してインストール」をクリック
- インストールが完了すると、再起動後にWindows11が起動します
インストールにはPCの性能やネットワーク環境によって数十分〜数時間かかる場合があります。業務時間中ではなく、できれば夜間や休日に実行するのが安全です。
アップグレードする際の注意点
アップグレードにはいくつかの注意点があります。特に会社で利用しているPCの場合、必ずシステム担当者に相談してください。
- アプリケーションの互換性
業務で利用しているソフトウェアがWindows11に対応していないと、利用できなくなる可能性があります。特に会計ソフトや業務管理システムは事前にベンダーに確認が必要です。 - 周辺機器のドライバ
プリンタや複合機、スキャナなどのドライバがWindows11に対応していないと使えなくなる可能性があります。 - 業務影響
アップグレード後に操作画面や設定方法が変わるため、社員への周知や簡単な研修が必要になるケースもあります。
アップグレードできないときの対処法
もしアップグレードに失敗した場合は、以下の原因と解決策を確認しましょう。
- システム要件を満たしていない
PCのスペックを再度確認。古いPCなら買い替えが必要です。 - HDD/SSDの容量不足
不要なファイルやアプリを削除し、十分な空き容量を確保してください。目安として20GB以上の空き容量が必要です。 - 互換性のないソフトウェアがある
一時的にアンインストールし、アップグレード完了後に最新版を再インストールする方法があります。 - ネットワークが不安定
Wi-Fiではなく有線LANで実行する、回線が安定した時間帯に実行するなどの工夫をしてください。
アップグレード作業がうまくいかない場合は、自力で解決しようとせず、早めに専門のITサポート会社やベンダーに相談するのが安全です。
会社でWindows10を使い続けるのは大きなリスクが伴う
ここまで見てきたように、サポート終了後にWindows10を使い続けることは、セキュリティリスクや業務停滞、法令違反の可能性を含めて大きなリスクがあります。
一方で、OSのアップグレードやPCの買い替えといった作業は、情報システム部門にとって大きな負担です。専任のIT担当者がいない企業では、なおさら準備や移行作業に手間取る可能性があります。そこで有効なのがアウトソーシングの活用です。専門のITサポート会社に移行作業を委託すれば、作業の効率化とリスク回避が同時に実現できます。結果として、自社の業務への影響を最小限にしながら、安全にWindows11へ移行することが可能になります。